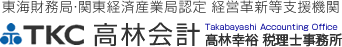パートらの厚生年金加入、企業規模要件を撤廃
2024年07月01日 :
会社経営
税理士の飯倉です!
6月26日の日経新聞の朝刊にこんな記事が出ていました
パートらの厚生年金加入、企業規模要件を撤廃
配偶者の扶養として年金が免除されていた人が
現状では従業員101人以上の企業に勤めている場合である条件を満たすと
厚生年金に入る義務が生じる
今年の10月から「従業員101人以上」の部分が「51人以上」に改正されることが決まっています
今回の記事はこの人数の基準を無くそうという話です
厚生年金の加入義務が生じた場合
働いている側とすると給料から厚生年金が天引きされることにより手取り額が減ることとなります
給料の金額によって厚生年金の金額は変わりますが
現状ですと最低でも月額8,052円が給与から天引きされることとなります
1年にすると最低でも96,624円です
この金額は給料が多くなるにつれて上がってしまいます
年間最低でも10万円近くの負担が発生することとなるため
少なくない金額ですね、、、
働いている側は厚生年金に加入することとなるため
将来受け取ることができる年金が増えることとなり
メリットも多少ありますが
実はこの改正は雇っている会社側の負担もあります
会社員が社会保険に加入している場合
給与から厚生年金や健康保険が個人負担分として天引きされますが
実は会社もその金額とほぼ同額を負担することとなります。
しかも会社側はただ負担が増えるだけで払ったことによるメリットは特にありません
※社会保険完備というのが今どきPRにならないと思いますし、、、
社会保険の会社負担は会社にとって決して少なくない負担です
特に従業員数人規模の会社で
今まで社会保険の負担が無かった従業員の分の負担が出たとすると
経営数字にも大きな影響を与えることが考えられます
この改正はいつから始まるかはまだ未定ですが
恐らくこの改正の方向で動くことになると思いますので
負担が増えたとしても企業経営に問題が生じないように
自社の稼ぐ力を鍛えるとともに無駄なコストは無いかを
常に自社の数字を把握しながら経営していっていただきたいです!

6月26日の日経新聞の朝刊にこんな記事が出ていました
パートらの厚生年金加入、企業規模要件を撤廃
厚生労働省はパートらの短時間労働者が厚生年金に加入する際の企業規模の要件を撤廃する方針を固めた。現在は従業員101人以上の企業に限定している。勤め先によって不公平が生まれないようにする。5人以上の個人事業所も全業種に厚生年金を適用する方向だ。2025年の通常国会に関連法案を提出する。
現行制度では従業員101人以上の企業に勤めるパートやアルバイトらが「所定労働時間が週20時間以上」などの条件を満たすと厚生年金に入る義務が生まれる。10月には51人以上の企業に広がる。
厚労省は7月1日に開く有識者懇談会で、企業規模要件について「撤廃の方向で検討を進めるべきである」とする案を示す。厚労省によると、新たに130万人程度が加入対象となる。実施時期など具体的な改正案は社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会で年末までにつめる。
配偶者の扶養として年金が免除されていた人が
現状では従業員101人以上の企業に勤めている場合である条件を満たすと
厚生年金に入る義務が生じる
今年の10月から「従業員101人以上」の部分が「51人以上」に改正されることが決まっています
今回の記事はこの人数の基準を無くそうという話です
厚生年金の加入義務が生じた場合
働いている側とすると給料から厚生年金が天引きされることにより手取り額が減ることとなります
給料の金額によって厚生年金の金額は変わりますが
現状ですと最低でも月額8,052円が給与から天引きされることとなります
1年にすると最低でも96,624円です
この金額は給料が多くなるにつれて上がってしまいます
年間最低でも10万円近くの負担が発生することとなるため
少なくない金額ですね、、、
働いている側は厚生年金に加入することとなるため
将来受け取ることができる年金が増えることとなり
メリットも多少ありますが
実はこの改正は雇っている会社側の負担もあります
会社員が社会保険に加入している場合
給与から厚生年金や健康保険が個人負担分として天引きされますが
実は会社もその金額とほぼ同額を負担することとなります。
しかも会社側はただ負担が増えるだけで払ったことによるメリットは特にありません
※社会保険完備というのが今どきPRにならないと思いますし、、、
社会保険の会社負担は会社にとって決して少なくない負担です
特に従業員数人規模の会社で
今まで社会保険の負担が無かった従業員の分の負担が出たとすると
経営数字にも大きな影響を与えることが考えられます
この改正はいつから始まるかはまだ未定ですが
恐らくこの改正の方向で動くことになると思いますので
負担が増えたとしても企業経営に問題が生じないように
自社の稼ぐ力を鍛えるとともに無駄なコストは無いかを
常に自社の数字を把握しながら経営していっていただきたいです!